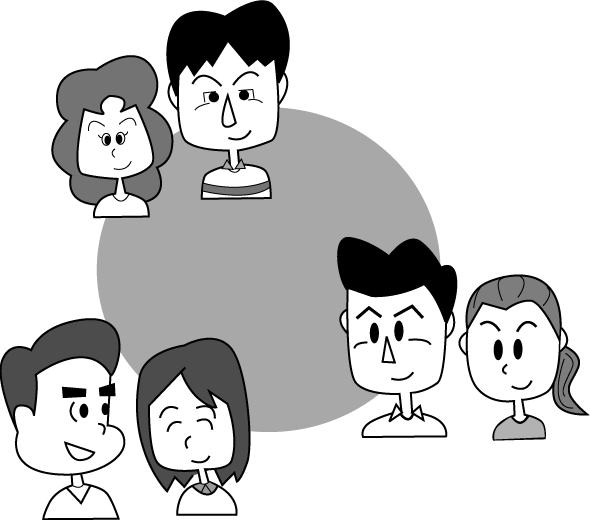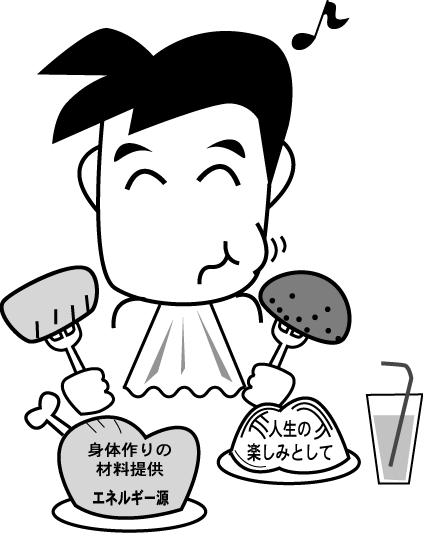| 筋疾患児の子育て Q&A |
| 【生活】 |
| Q14:筋ジストロフィーと診断され、不安でいっぱいです。どなたに相談したらよいのですか | ||
| A:筋ジスの患者さんを専門にみる国立療養所が全国に27施設あります。そこには、長期療養病棟があり、専門の医師をはじめ、多くのスタッフがいます。その他に「大学病院」「○○療育センター」「○○リハビリテーションセンター」等があります。この病気の患者さんを多く扱っている病院で相談することがよいと思います。 なぜ専門病院へ受診をお勧めするかといいますと、筋ジストロフィーは、各病型によって症状が異なり、それぞれが特有の経過を経ていきます。同じタイプでは、発症時期や進行の経過や症状に共通性があります。症状は一定の流れをもって進行していき、この経過の順序が入れ代わったりすることはありません。この症状の進み具合には個人差がありますが同じような時期に同じような状態になり、同じような医療的、訓練的対応や心理的援助が必要となります。このように多くの共通性をもつ筋ジストロフィーにおいては、まずこの病気の経過に伴った対応や予測のできる病院が必要です。そして、両親が心配している事柄を医者、看護師、訓練担当者そして、臨床心理士等に「よく話せる」そして、「よく説明をしてくれる」関係を作っていくことが大切です。 デュシェンヌ型の診断は幼児期に受けることが多いのです。子どもの診断を受けて間もない親は、ショックと不安の気持ちで混乱し、平常心を保つことが困難な程動揺されていると推測されます。子どもの為に何かしてあげたい、助けたい気持でいっぱいです。そのような気持ちがあるにもかかわらず、自分の気持ちの不安や混乱がうまく処理できずにこころを痛めていることと思います。 私はいままで、「誰かに、この不安や混乱した気持ちや戸惑いを話したい」と思っている多くの両親にお会いしました。親のこのような気持ちは自然なのです。不安いっぱいの気持ちを話すことは、気持ちを和らげる助けになります。親が元気になって、この病気の知識や知恵を身に付けていくことは子どもたちの力になり、効果的な援助になります。 私も専門病院の1つで筋ジスの患者さんや家族の方々の気持ちの対応を大切にして相談や心理的援助を行っています。援助の1つとして病院のかかり方のアドバイスもしています。その中でもっとも大切にしているのは、医師からの告知や病気の説明を受ける時は、両親の同席を勧めています。日本では子どもに関する事柄は母親の役割とする傾向があり、医師とのかかわりは母親が多いです。母親が動揺し、医師の説明の受け取り方に行違いが出てくる場合があります。その行違いをもったまま父親に伝えられると、その後の治療や両親が協力しあうことにも影響を及ぼしていきます。行違いをがないように両親で説明を受けるのが大切です。また、大きい出来事には付き添いあうことでショックを柔らげられます。この病気はお母さん一人で引き受けるのは困難です。お父さんと協力しあう出発の場として大切にしてください。 現在、前述の27の専門病院において心理的援助を専門とした臨床心理士は、非常に少ない状況にありますが、多くのスタッフが両親の不安の気持ちを援助してくれますので「話せる関係」をつくってください。 専門病院については日本筋ジストロフィー協会にご相談してください。 |
||
もどる |
||
| Q15:他の家族と交流を持ちたいのですが、どのようにしたらよいですか | ||
A:同じ疾患をもつ子どもや家族の方の交流はとても大切です。お互いに経験を話し合うことで「一人じゃないんだ」という気持ちが湧いてきて前向きな気持ちになっていきます。また、先輩達の子育ての「うまくいったこと」「失敗したこと」などの経験談を聞くことや見ることで「わたしにもできそう」「やってみよう」等知恵や工夫がでてきて子育てに役立ちます。また、子どもたちにとっても、色々な機能障害の子どもに出会うことにより自分のからだの状態を認識していく機会となります。それぞれの状態の子どもたちがお互いの機能を補い、助けあう場面を目にすることが多々あります。このような経験を通して子どもたちは病気を理解していきます。
|
||
もどる |
||
| Q16:病気について本人にはどのように話せばよいですか | ||
| A:この質問をよく両親から受けます。そのような時、私は「どのように話したいと思っていますか」とお聞きします。両親から「子どもには告知しました」「子どもにはみんな話してあります」あるいは「中学生になったら話そうと考えている」とそれぞれの考え方がおありのようです。「○○の時期に話した方がいい」「△才になったら話した方がいい」といわれてもなかなか統一のできない難しい事柄です。医師達の間でもこの件については慎重に論じられておりますが、統一した見解には至っていません。しかし子どもに病気を伝えることは大切だと多くの医師は考えています。 私はこのような相談を受けた時に、両親が病気をどのように理解し、受け入れることができているのか話し合います。まだ子どもの病気を受け入れられない親が子どもに病気のことを話すのは難しいと考えます。特にデュシェンヌ型のように幼い時期に発症する場合は、両親の病気の受け入れと理解がないと子どもへのよい援助は難しい傾向にあります。ですから親の病気への理解・受け入れの度合いは大切なのです。そしてこのことと同じように大切なことがあります。子どもの発達の成熟の度合いと子どもの個性などをよく捉えているかということです。病気を「話さなくては…話さなくては」という気持ちが優先されることのないようにしたいものです。これらの準備ができたらお子さんに合った時期にあった話し方ができるはずです。日々の子どもの発達や子どものこころのあり方を大切にし、理解しておくのが必要です。 親が十分理解し、受け入れられる状況になってくれば話すことができるようになります。子どもに病気を話すということは、子どもたちが自分の病気を理解して、自分で病気を管理していくために必要だと考えています。私達大人も自分たちの生命を管理をしています。子ども達も自分の機能の変化を知り、どのように対応し、何に気を付けていったらいいのか、そして自助具などが必要な時期になったら上手に取り入れて自分の身体の負担やハンディを補ってもらいたいのです。そして機能変化に伴う生活スタイルにも工夫する知恵をもってもらいたいのです。病気に適応していく上で病気の理解と受け入れは必要と考えています。子どもに病気を話すことの意味を両親で考えて、ここに書いたことを参考にしていただければと考えます。 |
||
もどる |
||
| Q17:成人になって、自立する方法はあるのでしょうか | ||
| A:自立にはいろいろな考え方があります。一般的には、他の援助を受けずに、「自分の力で身を立てること」「一人立ち」として捉えられています。このような自立を考えていらっしゃるのでしょうか? もし、一般にいわれる親から自立することを考えるとします。実際ボランティアの人たちの援助のもとで親から離れ、独立して暮らしている人たちがいます。彼等は自分達が年令と共に介助の比率が高くなり、親に替わる介助者の確保が必然的であると理解しています。彼等は、ボランティアの確保、生活費の確保、そして自分の生活スタイルにあわせたボランティアの介助体制などを考え工夫しています。時には、ボランティアの確保が少なく、介助が手薄になり我慢しなくてはならない状況も考え対処しています。このような自立をしていくには、ボランティアとのコミュニケーションや地域の公共機関との交渉など多くの社会性や知識が必要になってきます。このような能力を確保していくには小さい時から子どもの発達の成熟を促す課題の経験と訓練の積み重ねが必要です。しかし、筋ジストロフィーの子どもたちは病気であるため過保護な養育態度で育てられることが多くなります。機能障害により行動範囲が制約され、社会生活経験が少ないなど、病気の影響により、自立を促す経験の積み重ねが、同年令の子どもに比べて少ない状況にあります。 過保護な養育態度は、子どもが自分でやる習慣や工夫する能力を妨げていきますので子どもの発達や能力に沿った課題を身につけていく援助が必要です。例えば、幼児期でしたら、自分の身の周りを処理する能力を高め、小学生になったら、自分の出来ないこと出来ることを理解し、出来ないことは友だちにたのみ、工夫すれば出来ることは考え、生活に適応していく能力を高め、生活空間や交友関係を広げていく経験を多くもつこと、そして、自分のことは自分で伝える習慣を身につけることが大切です。これらの経験は、子どもたちが自信をもち、自分を信頼し、自分にあった自立を選択していく助けとなります。子どもたちが、どんな自立を考えて実行していくのか期待したいものです。 子どもの自立を援助するには、子どもの発達の良い時期に良い援助の出来る子育てが大切です。小さい時からの積み重ねは成人になったときに役立つことを確信しています。 (関谷智子) |
||
もどる |
||
| Q18:食事について、特に栄養について教えて下さい。 | ||
筋肉の再生に必要なたんぱく質は、多めにとるようにします。肥り過ぎも痩せ過ぎも好ましくありません。肥満や痩せの判定にはBMI(体重÷身長÷身長)という指標が使われます。たんぱく質所要量やBMI標準値の詳細、食べやすい食事の実際、作り方などは「筋ジストロフィー患者さんのための楽しい食事」福永秀敏監修、診断と治療社刊(ISBN4―7878―1256―4)に詳しく載っています。参考にされることをお勧めします。 食事は「楽しく、美味しく、安全に、必要量」摂ることが必要です。食卓の雰囲気作りや料理の色合い、盛り付けなどもとても大切です。そのためには工夫が必要です。協会を通じて、他のお母さんの経験や工夫を紹介してもらうのも良いと思います。 |
||
もどる |
||
| Q19:ものが飲み込みにくくなっています。どのように対処したらよいですか? | ||
| A:筋ジストロフィーは全身の筋肉が徐々に働きにくくなっていきます。ものを食べるときを想像してください。まず、目の周りの筋肉が働いて食物を見て、手や腕の筋肉が動き出して箸やスプーンを持って、食物をつかんで、口に持っていき、口や舌を動かす筋肉が働いてそれを受け取り、咀嚼して、のど(喉)の筋肉と一緒になって飲み込んで食道に送ります。食道の筋肉は食物を胃の方に送り、胃や腸の筋肉は消化・吸収を助けます。この間、身体を支える筋肉も働き続けていますし、呼吸するための筋肉も大忙しです。つまり、ものが飲み込みにくくなる(摂食・嚥下障害の)原因は、様々な身体の筋肉の機能低下の結果であることを知ってください。したがって、対処するときにはその原因を探って、適切な介助・工夫を行うことが求められます。 また、筋ジストロフィーの病型により、原因が異なることもあります。以下に、デュシェンヌ型(DMD)と福山型(FCMD)の摂食・嚥下障害の特徴と対策について述べます。DMDでは学齢期頃から、奥歯を噛みしめると前歯が噛み合わない(咬合不全)や舌が大きすぎて、口の中で食物をまとめにくいなどの障害が目立ってきます。したがって、前歯でかみ切らなければならない食物は加工して、一回に口に入れる量を少なくして、食事時間を少し長めに設定してあげることが必要です。青年期には、上記の特徴に加えて咀嚼、嚥下に関係する筋肉の障害により、一度で食物を飲み込めずに、飲み込む動作を繰り返したり(分割嚥下)、呼吸の異常により食事が長時間は続けられなくなったりします。栄養不足が問題となってくるのもこの時期です。したがって、対策は咀嚼しやすく、飲み込みやすい食事内容を多くして、食事の姿勢にも注意して疲労を防ぎ、呼吸障害に対する評価と治療をすることが中心となります。FCMDは食べる機能の発達自体に問題が起こりやすいので、早期から医療機関との連携が不可欠です。食べる機能は生まれてから様々な経験を経て獲得・発達していくものです。間違った食事介助を続けると、発達を阻害するばかりでなく、誤嚥により子どもを肺炎などの危険にさらすことにもなりかねません。発育に十分な栄養、水分量を保障しながら、食べる機能の発達を促す食事介助を行わなければなりません。専門家の力を借りて取り組んでいきましょう。 |
||
もどる |
||
| Q20:最近急にやせてきました。そのまま放置して良いのでしょうか。 | ||
| A:まず今の状態の評価をします。それぞれの病型と年齢に応じた痩せや肥満の評価基準(BMI)に照らして、今の状態が異常な痩せなのかどうかをみます。これはQ18でも紹介した「筋ジストロフィー患者さんのための楽しい食事」にBMIの表があります。そして、主治医により貧血や低蛋白血症、微量元素不足などが起こっていないかを調べてもらいます。この時、主治医は痩せていく病気の合併(甲状腺機能亢進症、消化器の病気など)も調べてくれるでしょう。それと同時に、体重の変化を記録してみて、何時から、どの様な経過で起こってきているかをみてみます。 これらをチェックして原因を探りますが、見過ごされやすいのは虫歯や歯周病などの口腔内の異常と気づかないうちに進行している呼吸不全、心不全です。口腔内の異常は、痛みを伴わない場合には自覚症状が少なく見過ごされやすく、「なんとなく食欲がない」という訴えのみの場合もあります。これは歯科の先生に対策をお願いしましょう。 食事と呼吸は同じのど(喉)という身体の一部を使って営まれることにより、呼吸不全の進行と食べる機能の低下は同時に起こることも多いのです。さらに、夜間の睡眠時に起こる呼吸不全は、熟睡が得られず朝の起床時の食欲の低下の原因となりますし、息苦しくなり不十分な呼吸を補うために使われるエネルギーの増加は痩せの原因になります。 心不全も、身体的な消耗を招き食事が困難になることは良く見られます。また治療のために食塩や水分制限が必要なこともあります。これも食事に影響します。したがって、急な痩せにはまず全身の検査をして原因を探り、適切な対処を行うことが求められます。主治医にすぐ相談してください。 (河原仁志)。 |
||
もどる |