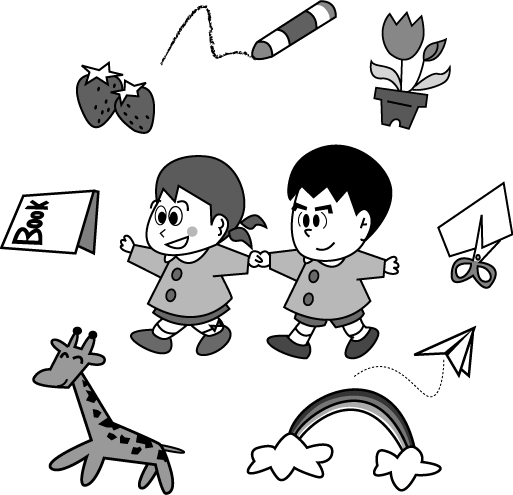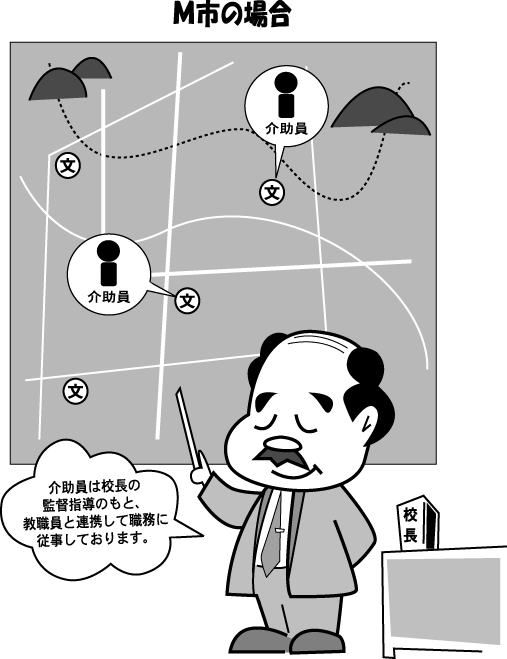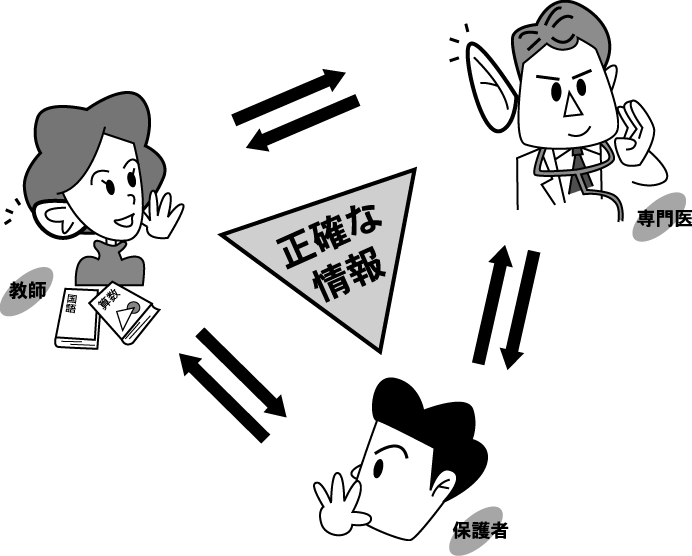| 筋疾患児の子育て Q&A |
| 【教育】 |
| Q21:幼稚園・保育園での生活の注意点を教えてください。 | ||
| A:幼稚園・保育園等での子どもの生活について、3歳から5歳までの3年間、病型はデュシェンヌ型筋ジストロフィーの幼児について書きます。 1.幼児期に育てたいこと 筋ジストロフィー児が一生で最も活発な運動機能を発揮するのがこの幼児期です。したがって、大切にすべきことは、他の幼児と同様に楽しく、活発に動く経験を十分にさせることです。病気が進行した後も幼児期に楽しく、皆で走ったことが仲間と共に活動し、共感する心を育てます。この共感性は人間関係の基礎として重要です。 2.筋ジストロフィー児の幼児期の不安 幼児期でも5歳頃になると軽い運動障害が出てきて、ジャンプができなかったり、お腹を突き出して腰を振って歩くのでからかわれたり、つまずいてよく転ぶこと等が見られることがあります。子どもの中に不安の芽が出てきて、時に周囲の人にあたることがあります。子どもの声に耳を傾けて、うなずきながら聞くように心がけましょう。
4.園での生活 幼稚園・保育園での生活は、できるだけすべて他の幼児と同じにさせる、同じに活動できるように内容を工夫することです。保護者の一部には皆と同じにやれないなら、かわいそうだから入園を遅らせようとか、在園時間や活動内容を制限しようとの話もありますが、これは子どものためになりません。確かに皆と同じくできない活動もありますが、子どもは自然と現状を受け入れて自分なりのやり方で参加します。時には仲間や保育師の助言にしたがって参加します。そうして、自分もできるという達成感を味わいます。ただ仲間も幼児ですので、手加減ができないこともあります。危険な場合は保育師等の大人が横に付いたり、筋ジストロフィー児には事故予防の目的で頭に保護帽をかぶせたり、膝や肘にサポータを付けたりすることもあります。また楽しい活動の後で足を痛がるために保育師から運動をさせていいのかと聞かれることがありますが、翌日に目立った疲労や痛みが残っていなければ、その程度の運動は支障がないとお考えくださいと私は答えています。さあ、皆と一緒に楽しく運動しましょう。 |
||
もどる |
||
| Q22:普通学級(学校)と養護学校のどちらを選べばよいですか? | ||
| A: 1.学級、学校をどのように選ぶか? まず結論から申し上げます。筋ジストロフィー児が学級、学校を選択する場合には、対象児の障害が運動障害のみか、他の合併障害があるのか、地域に適当な学級、学校が設置されているのか等が問題となります。実状を知るために、子どもの就学の対象となる学級、学校の見学会、体験入学等に親子で積極的に参加しましょう。また筋ジストロフィー児・者やその家族の集いに参加して、先輩達の経験を聞きましょう。それらの情報を基に子どもと家族で十分に話し合って決めれば、それが最良の学級、学校です。以下、筋ジストロフィー児が対象となる学級、学校について解説します。 2.障害児の学級、学校とは? 学校には通常の学校と盲・聾・養護学校があります。そして障害が軽い子どものために通常の小・中学校に特殊学級、通級指導教室があり、障害が比較的重い子どものために盲・聾・養護学校があります。特殊学級には障害の種類によって弱視、難聴、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、情緒障害があります。通級指導教室は特殊学級での教育対象となる障害の中で知的障害を除くすべての障害について設置できることになっています。養護学校には知的障害、肢体不自由、病弱の各養護学校があります。 3.筋ジストロフィー児の学級、学校選択の現状 筋ジストロフィー児は、障害が学校生活に支障がない時期は通常の学校を選ぶのが一般的です。しかし、学校生活に介助を要することが多くなると障害の状態と介助者の問題で学級、学校の選択に迫られます。運動障害のみの場合は、肢体不自由特殊学級への入級、必要に応じて通級による指導(通級指導教室)を受けることができます。障害が重くなると肢体不自由養護学校や病弱養護学校が対象となります。知的障害が重複している場合は、軽度であれば知的障害特殊学級、重くなれば知的障害養護学校があります。重複障害の場合は、障害の程度や学校環境等を考慮して適切な学校を選択することになります。地域に適当な学級、学校がない場合は、保護者と学校等で話し合って特殊学級の新設を要望し、地域で教育の場を確保できることもあります。平成14年度の就学基準の見直しで、比較的障害の重い場合も市町村の教育委員会が障害の状態に照らして、地域の小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認めた者(認定就学者)は地域の学校に就学できることになりました。これには教員の専門性と学校の施設・設備が整っていることが条件となっています。 4.結局、学級、学校を選ぶには? 以上の学級、学校についての現状を理解した上で、どの学級、どの学校を選ぶか考えて欲しいと思います。それぞれの学級、学校は一人ひとりの児童生徒に合った教育をするために設けられたものです。それぞれに長所がありますが、現状を見ると問題点もあります。繰り返しになりますが、子どもと保護者が直接に学校を見て、教育内容や卒業後の進路等について聞き、学校の施設・設備も見た上で、子どもと保護者が十分に話し合って、子どもの意思を尊重した結論を出すことが学校生活の充実には欠かせません。 |
||
もどる |
||
| Q23:養護学校の教育内容について教えてください。 | ||
| A: 1.教育内容の特徴 養護学校の教育内容も通常の学校と同様に新しい学習指導要領に変わりました。特筆すべきこととして、指導内容を基礎的・基本的事項に重点をおくこと、自立活動を中心に個別の指導計画を作成すること等があります。以下、平成14年度に文部科学省から出た就学指導資料の中から、教育内容に関する部分を抜粋してお答えします。なお、筋ジストロフィー児が実際に在籍することの多い、肢体不自由と病弱の養護学校の教育内容に限定して紹介します。 2.肢体不自由養護学校の教育内容 肢体不自由養護学校では、児童生徒一人一人の身体の動きやコミュニケーション等の状態及び発達段階や特性等に応じた指導を行っています。そのために、①小学校・中学校・高等学校の各教科を中心とした教育課程、②小学校・中学校・高等学校の下学年(下学部)の各教科を中心とした教育課程、③知的障害養護学校の各教科を中心とした教育課程、④自立活動を中心とした教育課程など、児童生徒の実態等を考慮した多様な教育課程を工夫して編成・実施しています。教育課程の編成に当たっては、教科等の通常の学校と共通するものに加え、自立活動の指導領域を設けています。自立活動で特に重視している指導内容は、身体の動きの改善・向上を目指すもので、これには座位の保持や起立・歩行に関する指導、日常生活動作に関する指導などがあります。また指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具を積極的に活用し、個別指導やグループ指導を重視しています。 3.病弱養護学校の教育内容 病弱養護学校では、教科等の通常の学校と共通するものに加え、自立活動の時間を設けています。自立活動では医療機関との連携を密にしながら、児童生徒が主体的に障害の状態を改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培うことを目標として、児童生徒一人一人の障害の状態や発達段階に応じた指導を行っています。またいくつかの障害が重複している場合には、児童生徒の実態に即して、可能な限り心身の調和的な発達を促すため、感覚、運動、言語など様々な側面の指導を総合的に行っています。 病気の治療や生活規制等のため、児童生徒には授業時数の制約、身体運動の制限及び経験不足などがみられます。このため教科指導においては、授業内容を精選したり、指導方法や教材・教具を工夫したりして学習効果を高めるように配慮しています。また児童生徒は身体活動を制限されることから直接的な経験が不足しがちなので、特別活動等の指導を通して、校内や校外において様々な経験が得られるよう配慮しています。 なお、病状が重いなどのため、学校に通学できない状態の児童生徒に対しては、教師がその病室に出向いて授業を行ったり、教室の授業の様子が映し出されるテレビ会議システムを活用して、病室などで授業を受けることができるようにしています。 |
||
もどる |
||
| Q24:学校での生活に介助員が要ります。介助員はつけていただけるのでしょうか? | ||
| A: 1.介助員って何? 介助員(地域により名称は異なります)については、文部科学省の規定といったものはなく、各市町村教育委員会で独自に設置しているようです。したがって、市町村によっては介助員の制度がある所、ない所があります。ご希望の方はそれぞれの地域の市町村教育委員会事務局へお問い合わせください。 また、介助員制度があっても、対象とする児童や学校等の範囲が地域によって異なりますので、肢体不自由の児童生徒が対象となっていること、希望する学校が介助員配置対象校になっていることも確認しておきましょう。実際には、介助員制度があっても地域の予算と希望のあった児童生徒数、対象校数等の間で調整することになります。したがって、早めに学校長や教育委員会へ介助員の希望を伝えておきましょう。その目的で市町村や県の教育委員会主催の毎年開催される教育相談に行かれるのも一案です。
各学校で児童生徒、保護者、教職員で話し合って、学校生活支援員事業の制度を利用しています。平成14年度は約40人の支援員が採用されているとのことです。もちろん支援員の配置を希望する保護者はもっと多いと思いますが、上記の調整でこの様な数になっているものと思います。個人的な印象として、支援員の有効活用が課題と思います。支援員の対象児童生徒に関する専門性の向上、対象児童生徒の積極的な学級参加を促すために他の児童生徒や学級担任との協力、学級担任についても支援員との連携、チームで教育する知識と技術の養成が必要です。 (長尾秀夫) |
||
もどる |
||
| Q25:学校生活で注意する点を教えてください。 | ||
| A: 1.子どもたちにとって学校とは 病気を持っていようと無かろうと、子どもたちの日常生活にとって学校という場は非常に大きな意味を持っています。学校を無視して子どもたちの生活を考えることはできません。したがって、筋ジストロフィーの子どもたちを診る際、ドクターも学校を常に意識しておく必要があります。一方、お父さんお母さんは子どもたちの学校での様子を正確にドクターに伝えなくてはなりません。 「遠足、運動会には参加するにはどうすればいいか」、「宿泊学習、修学旅行にはどんな注意が必要か」ところが案外ドクターは子どもたちの学校生活を知りません。それでは筋ジストロフィーの子どもたち(慢性の病気を持つ子どもたち)の主治医は務まらないのですが、現実は厳しいようです。解決策のひとつは筋ジストロフィー専門施設のドクターを主治医にすることです。
3.学校と話し合う中で「妥協することも必要?」 学校の先生とは様々なことで充分話し合うことが必要です。その際、子どもたちの学校生活をできるだけ快適にするためには、妥協することも大切です。例えば、校内の設備改善について考えてみましょう。これには予算が必要です。自治体の財政事情は相変わらずなかなか厳しいようです。何が何でもエレベーターを、といった態度はどうでしょうか。次善の策、といった考え方も重要だと思います。設備の問題は、無ければ無いで何とかなります。大切なことは、「この子を何とかしたい」と、いう気持ちを学校の先生方に持っていただくことです。 外交でラストワードは戦争を意味しますが、学校とのお付き合いでもラストワードは絶対避けなければなりません。 4.家庭と学校と病院と 最近、医療現場ではさかんにチーム医療という言葉が叫ばれています。ドクターだけの力は限られています。看護師さん、理学療法士、薬剤師、その他もろもろのスタッフが横並びで、ひとりの患者さんを中心に協力しあう、言ってみればごくあたりまえのことですが、あらためて叫ばれているのです。筋ジストロフィーの子どもたちのまわりでも、以前から医教連携が叫ばれてきました。学校と病院の一致団結です。しかしほとんどたてまえだけに終わっていたのではないでしょうか。今、ほんとうに必要なのは、ほんねの医教連携です。子どもたち、家族を中心とした医教連携なのです。しかし、これはあなた任せでは達成できません。まずはお父さんお母さん、気合いを入れ直し第一歩を踏み出してください。 |
||
もどる |
||
| Q26:養護学校へ変わりたいのですが? | ||
| A: 1.普通の学校? まずこの冊子を手にされた皆様方にお伺いします。 「養護学校に対してどのようなイメージをお持ちですか?」おそらく大多数の皆様方が極端なマイナスイメージをお持ちなのではないでしょうか。 「先生、普通の学校へ行かせたいのですが……」、筋ジストロフィーの子どものお父さんからこのような相談を受けました。「養護学校は普通でない?」と、いうことは、「その養護学校へ通う子どもたちも普通でない?」それはないでしょう。 「何が何でも普通の学校へやります」そうおっしゃる方、もう一度普通ということについて考えてみましょう。 2.手続きについて 参考図書を紹介します。「病弱教育Q&Aジアース教育新社」これはPARTⅠとPARTⅡが出版されていますが、いずれも手続きに限らず役に立つと思います。 転学については、まず担任の先生に相談することから始まります。したがって、前記図書は先生にとって必要な本というべきかもしれません。ただ、一つ付け加えるならば主治医の先生にも相談してください。医療情報の提供は非常に重要です。 3.養護学校への転校を考える前に 一口に養護学校といっても実はいろいろあります。病弱、肢体不自由、知的障害等ですが、筋ジストロフィーの場合は通常病弱養護学校ということになります。しかし実際には地域ごとにすべての養護学校がそろっているわけではなく、肢体不自由あるいは知的障害養護学校に通学している場合もまれではありません。学習に関しては教員配置等で考慮されているためあまり心配することはありませんが、問題は仲間です。共通の話題を話し合える同級生の存在が大切です。地元の知的障害養護学校へ通学していたけれど、「何か違う」と感じて、病弱養護へ再度転校となった友達もいます。さらに、もし同級生が一人もいないとしたら?もう一度転校を考え直してもいいかもしれません。 4.重複障害 例えば、筋ジストロフィーに加えて知的障害を有するような場合を重複障害と言います。筆者の個人的経験では、養護学校へ通う筋ジストロフィーの子どもたちに重複障害者が増えてきているようです。これは、単独障害であれば地元の学校へ通うケースが増えていることの裏返しでしょうか。重複障害の場合、よりプロフェッショナルな対応が必要であるのは言うまでもありません。さらに医学的にも緻密さが要求されます。重複障害は養護学校を選択する際のひとつのポイントかもしれません。 5.養護学校へ通う子どもたちの重症化 かつて、教育を受けることが困難または不可能な者と、体よく教育を受けることを拒否されていた就学猶予・免除の子どもたちは養護学校教育が義務化されて以来大幅に減少しています。これは高く評価されるべきことと思います。ただそのために養護学校へ通う子どもたちがより重症化しているのも事実です。学校での医療行為の問題もこの状況が大きく影響しています。そんな中でさらに積極的に障害児教育を推進していくためにはやはり医療の協力が不可欠でしょう。筋ジストロフィーの子どもたちの主治医は、学校からのアプローチを待つ姿勢では不充分です。おせっかいを焼いて、学校へ乗り込むくらいの積極性が必要ではないでしょうか。 6.「21世紀の特殊教育の在り方について」による提言 平成13年1月、文部科学省は21世紀の特殊教育の在り方についての最終報告をとりまとめました。そこでは個々の子どもたちのニーズに従った教育がうたわれています。かつて筆者の目には、悪しき横並びと映った養護学校教育も変化してきているようです。これを機に、願わくば養護学校についてのあまりのマイナスイメージが払拭されることを期待しております。 |
||
もどる |
||
| Q27:大学進学は無理ですか? | ||
| A: 1.大前提 この質問に答えるにはまず確認しておくべきことがあります。当然のことですが、学力の問題です。「それは任せてください!」と、いう答えを前提としてお話します。 2.情報は山ほど 実はこの問題に関してはすでに莫大な資料があります。インターネット使用が可能な方は、「大学における障害者の受け入れの現状」というキーワードで検索してみてください。書籍では、「大学案内障害者版」がほぼ毎年出版されています。各大学の簡単な受け入れ状況なら、WEB版でもみることができます。 大学でもっと勉強してみたいという希望を持っているのであれば、まずは自分で情報を集めてみることです。ひょっとしたらあなたはこのような情報を期待してこの冊子を広げたのかもしれませんが、少なくとも最高学府で学びたいと考えるのであればそれくらいは自分でやってみましょう。 3.大学とは 筆者自身のことをふり返ってみると、大学とはまったく職業教育機関そのものでした。医学部の場合はまず100%その通りでしょう。医学部で単に教養を身につけたいと思う方はいません。では、大学とはすべて高等職業教育を目的としているのでしょうか。再び筆者の経験をお話しします。大学に入学するとまず最初の2年間、教養学部に通いました。いや、通うはずでした。教養部とは直接医学には関係のない一般課目を勉強するところです。そこでは英語、ドイツ語とか化学、物理、数学といった必須課目と自分で選択できる選択課目がありました。語学は出席を取りましたからとりあえず教室には行きましたが、物理、数学は2回(最初の授業と試験)出席しただけでした。 実は今、大学でこの教養課程が消失しつつあるのだそうです。そもそも大学の歴史をさかのぼると、大学とは一般教養(リベラル・アーツ)を教える機関だったようです。日本でも、戦前の旧制高校、あるいは大学の教養課程がまさにその趣旨を受け継いだ学校でした。 さて、本題に戻ります。大学がリベラル・アーツを追求する機関とするならば、筋ジストロフィーであろうがなかろうが、そんなことは進学を考慮する際何ら妨げにはならないでしょう。一方、高等職業教育機関と考えるなら、「卒業しても就業できるのか?」と、いった横やりが入るかもしれません。そこで、ここは大学を本来のリベラル・アーツ追求の場として進学を考えてみましょう。 ところが、筆者の周りには国立大学工学部へ進学された方が3名います。また工業高等専門学校に進学された方もいます。ただし進学後の授業は相当厳しいことを覚悟しておいてください。ドクターストップが留年につながる可能性も充分あります。 4.その実際 自宅通学が可能かどうかは重大なポイントです。地元以外の大学へ進学したケースでは、いずれもお母さんが一緒に付き添い大学のそばに転居しました。 大学校内での介助については、少なくとも最初から全面的に大学当局に依頼するようでは先が思いやられます。学生ボランティアーを集めるのも良い方法でしょう。そんなとき、高校時代からそういう努力を体験しておくとずいぶん役に立ちます。筋ジストロフィーの場合、とかく周りが手を焼き過ぎるきらいがありますが、まず自分が先頭に立って行動を起こさなければ始まりません。入学前に大学から家族の付き添いを求められたケースがありました。家族から相談されたのですが、付き添っていないケースがあることをお教えしました。ただしこの場合はちゃんと本人がボランティアーを確保していました。 24時間、365日すべての時間にボランティアーを確保する困難さは容易にわかっていただけると思いますが、実際相当無理が生じます。つい最近も、どうしてもボランティアーが確保できず一人で過ごしていて姿勢を崩してしまい、十数時間倒れたままであったという事件を経験しました。 5.教室以外での学生生活 酒を飲むのもよし、仲間と徹夜で議論するもまたよし。旅行も大いに行くべし。(喫煙だけは絶対不可。これが守れないのであれば筆者は主治医をおろさせていただきます)。ただし事前に主治医にご相談下さい。酒は特に睡眠中の呼吸状態に大いに影響します。旅行にもそれなりの医学的準備が必要なことがあります。数年前ですが、「バンジージャンプをやってもいいか?」と相談にきた大学生がいました。筆者はあわてて、「そりゃ勘弁してくれ」と答えました。日頃から「主治医が頭を抱えるような相談を持ってこい、そうじゃないと退屈でしょうがない」と大きなことを言っていたので、たぶん彼は主治医をからかったのでしょう。ところで、現在筆者が恐れながらも期待している相談は、スキューバーダイビングです。 |
||
もどる |
||
| Q28:構内の設備についてどのように改善すべきかアドバイス下さい。 | ||
| A: 1.主治医の先生の役割 構内の設備改善には当然予算が必要です。通常学校の予算は事前に獲得しておかなければ、今必要だからすぐにというわけにはいきません。したがって病態の進行を予測して設備改善の予算を組んでもらわねばなりません。1年後には階段の昇り降りが困難になるだろう、といった予測です。こういった予測は専門病院の主治医の先生にしていただくのが最適です。いや、他の方ではおそらく不可能でしょう。場合によっては主治医の先生に直接学校と話し合ってもらう必要もあるでしょう 2.病態進行の予測の重要性 このような、先を予測しての設備改善が最も問題になるのは小学校です。デュシェンヌ型筋ジストロフィーでは通常9、10歳頃車いす導入の検討が必要になります。学校生活においてこの車いす導入は非常に大きなターニングポイントとなります。少なくとも予算請求の半年前にはこの予測をしておく必要があるでしょう。
3.具体的に、何を改善すればいいの? (1)トイレの改善 現状でも多くの学校でトイレの改善は行われているようです。手すりをつける、洋式にする、段差をなくする、手洗い用水道の改善、細かい点はいろいろありますが、案外忘れられていることがあります。それは介助に必要なスペースを充分に確保することです。このためにアコーデオンカーテンを使うのも一つの方法です。狭いスペースで無理をして介助し、腰痛に悩まされる先生も少なくありません。 (2)段差の解消 生徒用玄関、校庭への出口、通常学校にはありとあらゆるところに段差があります。筋ジストロフィーの子どもたちにとって、ほんの数センチの段差でもつまずきの原因となります。また車いす導入後は段差が致命的障害となります。できる限りスロープを設置していただきたいものです。車いすで利用できるスロープには条件があります。幅はもちろんですが、その傾斜が問題です。特に介助なしで自走する際には注意が必要です。 (3)教室の問題 小学校では学年があがると教室が上の階に移動することがよくあります。ところが病態の進行によりまず困難になるのが階段の昇降なのです。手すり設置が欠かせなくなります。しかし、車いすになると手すりも役に立ちません。もしエレベーターがあれば何も問題はありませんが、既存の建物に新たにエレベーターを設置するには莫大な予算が必要です。次善の策にならざるを得ないことも少なくありません。 (4)階段昇降機 階段問題の最も現実的な解決策は昇降機ということになるでしょう。しかし階段昇降機についてはぜひ知っておいていただきたい点があります。なお、ここでいう階段昇降機とは移動式のものです。階段に取り付けるタイプのものは姿勢保持に問題のある筋ジストロフィーではまったく役に立ちません。また、駅などに装備されている本人の車いすごと運べるものは、学校ではスペースの問題等でやはり使用が困難です。移動式階段昇降機は現在日本で二社の製品が使用可能です。ひとつはドイツ製ですが、こちらは専用の車いすを使う必要があり、筋ジストロフィーの子どもたちが使用するのは非常に不便あるいは不可能です。 国産メーカーでは現在三種類の階段昇降機が販売されています。さて、その選択に当たっては非常に重大なポイントがあります。一般に車いすといえば足の不自由な方と連想されます。しかし筋ジストロフィーでは、全身の筋力が低下していきます。最初は手こぎの車いすで充分でもすぐに電動車いすが必要となります。さて、エレベーターの設置されていない地域の学校で電動車いすを使用する際には簡易型電動車いすが重宝します。この簡易型電動車いすが使用できることが、階段昇降機選択に非常に重要なポイントとなります。その結果、機種は自ずと決まってきます。 4.ハードよりもソフト 構内の設備(ハード)の改善(バリアーフリー化)が重要であることはいうまでもありませんが、実はもっと重要なことがあります。それは考え方のバリアーフリー化です。予算請求を伴う設備の改善にはなかなか思うに任せずいらいらすることもあります。しかし、ソフトのバリアーフリー化ができていれば案外何とかなるものです。あせらずにがんばりましょう。 (多田羅勝義) |
||
もどる |